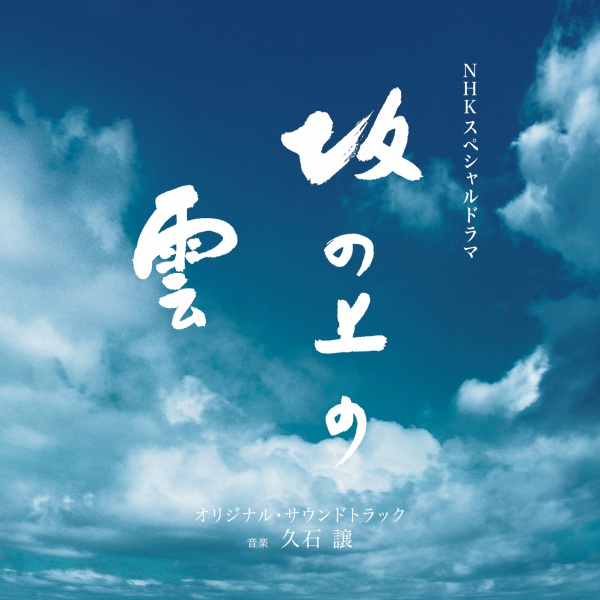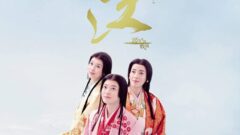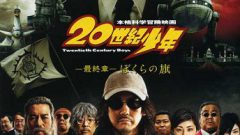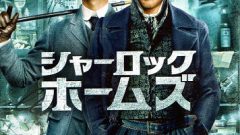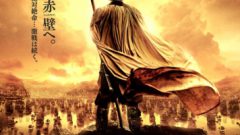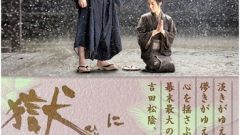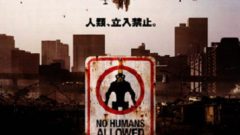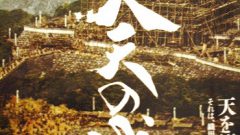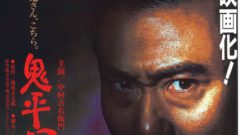第1回
いよいよ始まりました。明治時代の日露戦争を舞台にしたスペシャル大河ドラマです。
原作がしっかりしていることもあり、期待通りの第1回でした。
「坂の上の雲」という題名は「あとがき」書かれています。
『のぼってゆく坂の上の青い天にもし一朶の白い雲がかがやいているとすれば、それをのみみつめて坂をのぼってゆくであろう。』
こうした言葉もナレーションで多用しており、原作の世界観を忠実に再現しようとしている姿勢は評価できます。
この物語は『まことに小さな国が、開花期をむかえようとしている。』で始まり、『この物語の主人公は、あるいはこの時代の小さな日本ということになるかもしれないが、ともかくもわれわれは三人の人物のあとを追わねばならない。』と続きます。
原作を読まれた方には、ごく当たり前のことですが、「坂の上の雲」の本当の主人公は『この時代の小さな日本』です。
そして、ナレーションでも語られたように、大きな主題が日露戦争です。
司馬遼太郎氏は、本書でこう宣言しています。
『余談ながら、私は日露戦争というものをこの物語のある時期から書こうとしている。
(略)この小さな、世界の片田舎のような国が、はじめてヨーロッパ文明と血みどろの対決をしたのが、日露戦争である。
その対決に、辛うじて勝った。-(略)-いまからおもえば、ひやりとするほどの奇蹟といっていい。
その奇蹟の演出者たちは、数え方によっては数百万もおり、しぼれば数万人もいるであろう。しかし小説である以上、その代表者をえらばねばならない。
その代表者を、顕官のなかからはえらばなかった。
一組の兄弟をえらんだ。
(略)秋山好古(よしふる)と秋山真之(さねゆき)である。この兄弟は、奇蹟を演じたひとびとのなかではもっとも演者たるにふさわしい。』
「坂の上の雲」のあらすじはこちらで紹介しています。
補足として「殉死」も読むのがおススメです。

第2回
ドラマとしての出来は予想以上です。
前回、松山を出てきた秋山真之と正岡升の二人は大学予備門を受けました。升はよほど運がいいらしく受かってしまいます。真之も受かります。
やがて二人は共同で下宿生活をおくることになります。
ですが、真之は悩んでいました。
真之は好古に、いまのまま大学予備門にいれば結局は官吏か学者になるだろうが、第二等の官吏、第二等の学者だろうといいました。
真之は「あしはどうも要領がよすぎる」というのです。
選んだ道は海軍でした。
子規の顔がうかんで、思わず涙がにじみます。
海軍兵学校の同期は五十五人。真之の入学時の成績は十五番目でしたが、一学年が終わると首席になり、それを通しました。
このくだり、ドラマでは入学時は十四番と言っていたような気がします…。
当時の明治海軍は艦船六隻から出発しました。
海軍兵学校での会話のほとんどは英語だったそうです。海軍といえばイギリスの時代だったのです。
逆に陸軍といえばドイツでした。
ドイツ様式を取り入れている陸軍大学校在籍中の好古にとって問題が生まれます。
それは旧藩主久松家の当主・定謨がフランスの陸軍士官学校に入るので同行できないかというのです。
それに自費によるフランス留学です。ですが、好古は陸軍における栄達をあきらめ承諾しました。
好古の栄達は陸軍大将までで、元帥にはなれずに終わっています。
明治二十年七月。好古はフランスへ留学しました。
日本陸軍は満三十になったかならずの若い大尉に、騎兵建設の調べを全て依頼したようなものであり、同時に帰国すれば好古自身がその建設をしなければなりませんでした。
『まことに小さな国が、開花期をむかえようとしている。』
まだ、大河ドラマは始まったばかりです。
第3回
肺結核におかされた正岡升は「子規」と号するようになります。子規とは「ほととぎす」。血に啼くような声に特徴があり、喀血した自分にかけたのです。
明治の当時、結核は不治の病です。長い時間が与えられていないと悟った子規の活動が本格化しだします。
この子規を死の間際まで看病して、その最期を看取ったのが、妹の律でした。律は結核になった子規のため、松山から上京しました。
一方で、政治的には朝鮮半島をめぐって、清国との対立が表面化します。
後世、日清戦争はやむにやまれぬ防衛戦争ではなく、あきらかに侵略戦争であり、日本においてははやくから準備されていた、といわれましたが、首相の伊藤博文にはそういう考え方はまったくありませんでした。
ですが、参謀次長川上操六にあっては、あきらかにそうでした。川上操六は骨のずいからのプロシャ主義者でした。
川上操六と同じ思想を持つ者に外務大臣陸奥宗光がいました。
二人は内々で十分な打ち合わせをとげており、川上操六は短期決戦であれば成算ありと結論を得ていたので、短期に大勝を収め、講和へ持って行くことは陸奥が担当することになりました。
二人がやった戦争といっていいでしょう。
「坂の上の雲」の中で、司馬遼太郎氏は語る。
『日清戦争とはなにか。
その定義づけを、この物語においてはそれをせねばならぬ必要が、わずかしかない。
そのわずかな必要のために言うとすれば、善でも悪でもなく、人類の歴史の中における日本という国家の成長の度あいの問題としてこのことを考えてゆかねばならない。』
『あいかわらずの帝国主義はつづくが、-(略)-いわばおとなの利己心というところまで老熟した時期、「明治日本」がこのなかまに入ってくるのである。』
『日本のそれは開業早々であるだけにひどくなまで、ぎごちなく、欲望がむきだしで、結果として醜悪な面がある。』
こう、帝国主義下の日本を語り、続いて今回のドラマにも登場した参謀次長の川上操六について語っています。
『川上操六は骨のずいからのプロシャ主義者といっていい。-(略)-参謀本部の活動はときに政治の埒外に出ることもありうると考えており、ありうるどころか、現実ではむしろつねにはみ出し、前へ前へと出て国家をひきずろうとしていた。-(略)-川上の考え方は、その後太平洋戦争終了までの国家と陸軍参謀本部の関係を性格づけてしまったといっていい。』
この川上操六が性格づけた国家と陸軍参謀本部に続くかたちで、当時の憲法を語っています。
『憲法-(略)-によれば天皇は陸海軍を統率するという一項があり、いわゆる統帥権は首相に属していない。作戦は首相の権限外なのである。このことはのちのちになると日本の国家運営の重大課題になってゆくのだが、-(略)-はるかな後年、軍部がこの条項をたてに日本の政治のくびを締め上げてしまうにいたろうとはおもわなかったであろう』
『明治憲法-(略)-がつづいたかぎり日本はこれ以後も右のようでありつづけた。とくに昭和期に入り、この参謀本部独走によって明治憲法国家がほろんだことをおもえば、この憲法上の「統帥権」という毒物のおそるべき薬効と毒性がわかるであろう』
第4回
日清戦争がはじまりました。ドラマでは描かれていませんが、原作で描かれている個所を補足してみます。
日清戦争の当時、秋山真之は海軍少尉で、巡洋艦筑紫の乗組員でした。
海軍はこの戦役からはじめて連合艦隊方式をとりました。司令長官は伊東祐亨。
海軍は三つの水域で清国艦隊と海戦をして、それぞれの水域で世界の海戦史上記録的な戦勝をあげることになりますが、真之はまったくの素人だと批判しました。伊東も戦後「天佑」であるとしています。
この海戦は世界中から注目されていました。久しく大規模な海戦がなかったのもあり、近代海戦の実験という意味合いもあったからです。
列強海軍の専門家のほとんどは清国艦隊が勝つと予想していました。
晩年、秋山真之は宗教に傾倒したそうです。戦争の悲惨さというものが真之の心をむしばんだのです。
その晩年の真之を示唆するように、ドラマでは目の前で兵が死んでいく姿に強く心を傷つかせる姿が描かれています。
そして、自分は軍人に向いていないという独白もさせています。恐らく秋山真之という男は、本人の言うとおり、軍人には向いていなかったのかもしれません。
一方、騎兵第一大隊長になった秋山好古は旅順要塞に向かって進みました。
旅順の攻略には半年はかかるといわれたが、まる一日で陥ちてしまった。清国兵士の士気の低さによるものでした。
この攻略に関わった乃木希典と伊地知幸介が後年再び旅順攻撃の指揮をとることになります。
原作を読まれた方には周知のことですが、この二人について司馬遼太郎氏の評価は低いです。
とくに伊地知幸介に関しては無能以下の評価を下しています。
さて、従軍にこだわった子規も無理を押して従軍しました。
ですが、子規の従軍はごくわずかな期間で終わります。そして、帰国後、子規は療養生活を余儀なくされます。
第5回
大河ドラマらしいドラマです。歴代の大河ドラマの中で、間違いなく五指に入る出来です。
そのドラマも今年度分は第5回が最後で、第6回から第9回は2010年12月の放映となります。
第5回は秋山真之のアメリカ留学と広瀬武雄のロシア留学が軸となって語られ、それに、正岡子規の晩年を苦しめた脊椎カリエスの発症と、発症後の子規の姿が描かれました。
日本は日清戦争の結果、二億両の賠償金と、台湾、遼東半島などを得ました。このうち遼東半島はロシアの横槍によって返還を余儀なくされました。
ロシアは極東進出の大きな眼目として不凍港の獲得がありました。それには満州を得なければなりません。遼東半島はロシアのものとなり、明治三十一年三月十五日調印されました。
日本はとうていロシアと戦えるような国ではありません。実力がなければそのいいなりになるしかありません。
秋山真之はアメリカに留学しました。アメリカではキューバの問題が加熱しており、米西戦争直前の時期でした。
真之は米西戦争で、アメリカ艦隊がスペイン艦隊を軍港にとじこめ、港口に汽船を自沈させた、世界最初の閉塞作戦をその目で見ることになりました。この実見がのちに日露戦争で生きることになります。
真之の書いた米西戦争のレポートは、真之の持つ戦術能力を海軍省と軍令部につよく印象づけることになりました。
レポートは、日本海軍がはじまって以来、終焉するまで、これほど正確な事実分析と創見に満ちた報告書はついに出なかったといわれるものでした。
のちに、真之が東郷艦隊の参謀にえらばれ、艦隊の作戦は秋山にまかせると信用を受けるようになる始まりです。
子規が晩年を過ごした根岸の借家を、だれいうとなく子規庵と呼ぶようになっていました。
病床についてからの子規の文筆活動は凄まじく、俳論と俳句研究などにより、俳句革新はほぼ成し遂げられました。
ドラマでは詳しくは描かれていませんが、俳句の次に子規が挑んだのが、短歌でした。
当時の短歌は知識階層の手に握られていました。相手は知識人だけに、簡単にはゆきませんでした。ですが、子規は最初から挑戦的でした。
子規は、わずかな例外を除いて和歌というものはほとんどくだらぬと言ってのけ、そのわけを様々に実証します。
その当時の子規に帰国した秋山真之は触れています。
真之は子規の書いたものを寝転がって読み、読み進めるうちに、子規の革新精神のすさまじさと、たけだけしい戦闘精神に酔ったごとくとなります。
そして、子規が俳句と短歌というものの既成概念をひっくりかえそうとしていると感じました。
大河ドラマ
2009年公開のドラマ・映画