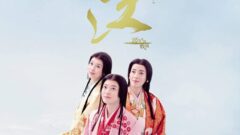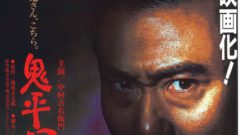2023年の大河ドラマの舞台は戦国時代から江戸時代初期、主人公は徳川家康です。
ドラマは1560年の桶狭間から始まりました。徳川家康は1616年に亡くなりますので、56年間を、1年間で描くことになります。
徳川家康を主人公とした大河は、第21回(1983年)「徳川家康」、39回(2000年)「葵 徳川三代」以来、3回目です。
前年(2022年)の「鎌倉殿の13人」の最終回で徳川家康が登場して話題になりました。
「どうする家康」には原作はありません。オリジナル脚本です。
脚本家は古沢良太(こさわ りょうた)さんです。
ALWAYS 三丁目の夕日(2005年)や探偵はBARにいる (2011年)、コンフィデンスマンJPなどを手掛けてきました。
コミカルもうまく取り入れることができる脚本家です。
時代考証は小和田哲男さんと平山優さん、柴裕之さんです。
平山優さんはTwitterで頻繁に情報を発信していらっしゃいます。フォローすると色々な裏話聞けるかもしれません。
ドラマの舞台となる時代については下記にまとめています。ご参照ください。
あらすじ/ネタバレ/雑学
第1回 どうする桶狭間
ドラマは1560年の桶狭間の戦いから始まりました。
松平元康(のちの徳川家康)は、数えで19歳。満17歳。
織田軍と今川軍との争いの中、味方のいる大高城へ、兵糧を運ぶ任を任されます。兵糧を運び込むためには、敵陣を突破しなければなりません。
一方で、今川家は今川義元自ら指揮をして織田軍と戦うつもりで出陣しましたが…。
初回から怒涛の展開でした。
疾走する馬にまたがった織田信長が、今川義元の首を槍の穂先にさして、その槍を投げるシーンには驚きました。
そして、戦場に野晒しの状態で転がっている今川義元の首…。
今川家は足利家に連なる名家なんですが…
最近の研究で織田信長像もだいぶ変わってきていますので、果たして首を転がしたままにするでしょうか…
さて、ナレーションでは「神君・家康」と称えながら、ドラマで描かれる姿は、弱虫、泣き虫、へなちょこな殿様です。コミカルな脚本です。
意外だったのが、瀬名(のちの築山殿)との関係です。
イメージとして、正妻・築山殿と家康の関係は良くない、というのが頭にありましたので、互いに好いて結ばれたという設定が意外でした。
とはいえ、人の心は移ろうものですので…。
また、初回から重要な登場人物が目白押しでした。徳川家康を支える多くの人物が登場しました。
石川数正、酒井忠次(徳川四天王)、鳥居元忠、大久保忠世、平岩親吉…、そして本多忠勝(徳川四天王)。
ところで、夏目広次ってどなた?
調べてみると、三方ヶ原の戦いで活躍したようです。
初回に関して時代考証の平山優さんのTweetが参考になります。
https://twitter.com/HIRAYAMAYUUKAIN
- (1)家康はただの人質ではない。そして惨めな駿府時代を送ってはいないことを表現する。(中略)惨めな人質生活というのは、江戸時代に創作されたものでしょう。家康が幼い頃から惨めで苦労したとすることで、天下人に登り詰めたことが一層引き立つからです。
- (2)家康は、今川義元から極めて大事にされていた(中略)当時ならば、築山殿の方が家康よりも格上でした。なんと言っても、今川一門ですからね。これにより、家康は今川一門格となり、地位が向上します(中略)家康と氏規は相婿の関係となり、今川一門衆となります。義元がこうした婚姻を実施したのは、男子の兄弟がいない氏真を支える一門として、家康と氏規を考えていたでしょう。
- (3)大高城は当時海岸近くにあった。
- (4)大河ドラマは、歴史を舞台にしたヒューマンドラマであり、群像劇です。大まかな年表としての出来事は外さず、物語が展開していきます。ですが、ドラマとしての内容は、フィクションです。端的に申し上げれば、同じ徳川家康を題材にした専門の歴史書と歴史小説は違うのと一緒です。
- (5)家康と岡崎家臣との関係は、徐々に形成されていったもの(中略)家康は駿府で成長しており、岡崎の家臣らとは距離がありました。だから、顔もみたことのないとか、おぼえていないとか、うっすら記憶にあるとか、それが実際のところ。(中略)家康は駿府で成長しており、岡崎の家臣らとは距離がありました。だから、顔もみたことのないとか、おぼえていないとか、うっすら記憶にあるとか、それが実際のところ。
第2回 兎と狼
織田信長の描かれ方は、真っ赤な衣装を含めて、賛否両論ありそうです。
でもまぁ、ドラマですから。
さて、大高城で織田信長軍に囲まれ、松平元康勢は孤立しますが、なぜか織田信長は引き揚げます。
岡崎城から今川勢が逃げ出したことを聞いた家臣らは、岡崎に帰ろうと言いますが、元康は駿府に戻ると聞きません。
ですが、駿府に戻ろうとする途中で、大草松平家の松平昌久に襲われ、命からがら菩提寺の大樹寺に逃げ込みます。
ここにいたのが、榊原小平太(のちの榊原康政)でした。徳川四天王の一人です。(残るは井伊直政だけです)
大樹寺を松平昌久に囲まれた元康は先祖の墓の前で自害しようとします…。
先祖の墓のあるところから見える「厭離穢土 欣求浄土(おんりえど ごんぐじょうど)」の文字。
徳川家康の馬印に用いられたことで知られています。
ドラマでは「汚れた世を浄土にすることを目指す」という意味で語られました。
さて、寅の年、寅の日、寅の刻に生まれた徳川家康ですが、ドラマで実際は兎の年に生まれたのを、数日ずらして寅の年生まれにした、と描かれました。
寅のように強い大将は表向き、実は、兎のように臆病で警戒心が強い大将、というのがドラマの松平元康になりそうです。
第3回 三河平定戦
松平勢はいつまでも来ぬ今川軍に不信感を抱き始めます。
家臣は今川を裏切って織田に寝返ることを考え始めますが、元康は駿府に残した妻子が心配でなりません。
そんな中、元康を訪れてきたのが伯父の水野信元と母・於大でした。
水野家は神君・家康公の恩母君の実家です。江戸時代には、譜代大名の一つになります。
この水野家からは幕府の老中が出ており、天保の改革の水野忠邦が有名です。
とはいえ、水野信元の直系子孫ではありません。水野信元は水野忠政の次男で、四男の水野忠守の家系から水野忠邦が誕生します。
阿部寛演じる武田信玄が話題になりました。約1分程度の短いシーンに「テルマエ・ロマエ」を彷彿させたため「テルマエ信玄」と沸き上がりました。
そして描かれた躑躅ヶ崎館は、ジブリ感が強い出来上がりでした。実際の躑躅ヶ崎館は↓こんな感じです。

織田信長や、武田信玄、飯富昌景の人物造形は、従来型の人物像をデフォルメした印象です。演出側のスタッフのイメージがそうなでしょうか…。
第4回 清州でどうする!
暗雲立ち込める清州城へ織田信長に会いに行く松平元康一行は、中国の宮殿さながらに巨大な中庭があり、2段上に豪華な建物がある城に驚きます。
これには見ている方も驚きました。
脚本では「1562年(永禄5年)1月清須城 城門が開いてゆく。到着している元康、左衛門尉、数正、彦右衛門、七之助、平八郎ら、みな唖然としている」としか書かれていません。
https://twitter.com/hirayamayuukain/status/1620355059505860615?s=46&t=83sl88asuDjQAn5crqZmVw
演出、美術、技術スタッフの解釈で、宮殿になってしまったようです。
初回から織田信長が登場するシーンは、何やら禍々しさがある感じで続いてきておりますが、第六天魔王をイメージしているのでしょうか。
さて、初登場となるお市と元康は、元康が織田家にいたころからの顔なじみで、お市が恋心を抱いていたという設定でした。
そのお市が元康を連れて清州城下を一望できる丘に連れていき、清州の発展を見せつけます。
ですが、残念なことに、清州周辺には城下を一望できる丘はありません…。
お市同様に初登場の木下藤吉郎は、時折見せる裏表のある表情に狂気を感じました。今後に期待が持てそうです。
妻の瀬名を駿府に残していることに気が気でない元康ですが、その瀬名を奪い取ろうとする今川氏真はあまりにもゲスでした。
松平元康が今川から離れて織田方についた決定打は、今川氏真に怒りを覚えたからでした。
そして、今川家を滅ぼす決意をしたのです…
第5回 瀬名奪還作戦
この5回目は必要な回だったのでしょうか…。
第6回目と一緒にすれば良かったのではないかと…
ドラマの本筋に一切関係せず、新しい登場人物を紹介しただけの感じで、本筋は次回へ持ち越しとなりました。
さて、駿府にいる瀬名と子供たちを取り戻すために、大久保忠世の推薦で本多正信が登場しました。
本多正信は、家康、秀忠と2代にわたって徳川政権の中枢を支え、家康からは唯一「友」と言われた家臣です。
陰謀・策謀型の人物の印象がありますので、陰鬱な感じのイメージがありますが、ドラマではテキトーな感じの人物として登場しました。このキャラのまま行くのでしょうか?
本多正信は瀬名親子を盗み出すつもりで、服部党の服部半蔵に依頼をします。
服部半蔵は忍者の元締めのイメージですが、武士であり、徳川十六神将の一人です。
今の皇居(江戸城)半蔵門の由来となった人物でもあります。(半蔵門由来には諸説あります。)
ですが、盗み出すことに失敗します。
第1回で大高城へ兵糧の運び込みを行った際の城代・鵜殿長照(うどの ながてる)が妹・お田鶴(おたづ)を使って、関口家の動向を探り当て、待ち伏せしたからでした。
第6回 続・瀬名奪還作戦
前回、奪還作戦を失敗した服部党でしたが、今回は上ノ郷城を攻め、今川一門の鵜殿長照、息子の氏長、氏次兄弟を生け捕りにして、交換する作戦を立てました。
新たな登場人物として、服部党の忍びとして女大鼠、そして、第2回で登場した榊原小平太が松平の小姓として再登場します。
上ノ郷城攻めで忍びを使ったことや、人質の交換というのは、その通りのようで、うまく演出されていたように思います。
家康の癖とされる、指(もしくは爪)を噛む癖や、貧乏ゆすりもさりげなく描かれていました。
この回を見て、やはり前回第5回は不要だったように思えて仕方ありません…。まとめてしまえば、スピーディな展開で、一層面白かったように思います。
第6回までの時点で、時代考証を担当している先生方へ筋違いの批判がありました。時代考証は、あくまでもアドバイザーであり、採用・不採用は制作側の脚本家や演出担当のマターです。
ドラマを面白くするのも、つまらなくするのも、制作側の脚本家や演出担当です。
脚本が凄く面白いわけではないですが、第5回までは演出側の責任が強いように思います。第6回は良かったと思いました。
第1回~第5回までの演出スタッフは、時代劇や歴史ものがお好きではないのでしょうかねぇ…。
第7回 わしの家
この回で名を元康から家康に改名しました。
三河を一つの家と見立てての改名でした。
さて、家康を悩ましたのが三河の一向一揆でした。
この回からその試練が描かれ始めます。相手は蓮如の曾孫である空誓です。本證寺を拠点としています。
ドラマでは寺を中心に寺町を塀で囲ったさながら城郭のような様相が描かれました。
すごい賑わいに家康、本多平八郎、榊原小平太の主従も驚きます。
新たな登場人物は、槍の半蔵こと渡辺半蔵守綱です。徳川十六神将の一人です。
第8回 三河一揆でどうする!
前回から始まり、今回で本格化した三河一向一揆ですが、徳川家康の三大危機の1つとされます。
家康の三大危機は、三河一向一揆、三方ヶ原の戦い、伊賀越えです。
三河一向一揆では家中から一向一揆勢に寝返るものが出て、代表的なところで本多正信、渡辺守綱らが家康と敵対しました。
ドラマでは、吉良義昭と松平昌久が一向一揆と連動して家康を追い込んだように描かれましたが、両者は連動していなかったとも考えられているようです。
一向宗は日本には珍しい一神教の色彩の強い宗教でした。
戦国時代にキリスト教が伝来しますが、宣教師はバチカンへライバルになるのは浄土宗(一向宗)であると報告しました。
オロオロするばかりの家康ですが、さて、どうするのでしょう。
第9回 守るべきもの
この回で三河一向一揆が終わりました。この三河一向一揆では、後悔しっぱなしの家康が描かれました。
オロオロし、後悔し、臆病で、小心者の、情けない家康しか描かれていませんが、この先はどのようになっていくのでしょうか。とりあえず、ここまでの家康には魅力を感じません…。
一向宗側についた家臣を不問に付し、元通りの家臣として扱いました。渡辺守綱などは、後年徳川十六神将に数えられるほどの活躍をします。
一方、この一揆のあと、しばらく徳川家を離れるのが本多正信です。徳川家に帰参するまで方々を渡り歩いたようです。
三河一向一揆の中心となった空誓の側にいた千代ですが、望月千代であることが明かされました。武田信玄が一向一揆を扇動するために送り込んだのでした。
相変わらず、躑躅ヶ崎館のジブリ感は強いままです。背景に鹿が出てこようものなら、シシ神様が出たと大盛り上がりになったことでしょう。どうせなら、こういう演出もやってみません?
巫女を統括し、諸国の情報を集め、武田信玄に報告していた人物としてゲームなどでも著名ですね。ただ、夢を壊すようで心苦しいのですが、望月千代女は架空の人物です。長野県に伝承と史料が伝わっていますが、少なくとも武田氏関係のものは、当時のものではありません。
https://twitter.com/HIRAYAMAYUUKAIN/status/1632384253408460801
第10回 側室をどうする!
ストーリーラインから断絶している回です。必要だったのでしょうか?
さて、この回では家康の側室選びが描かれました。
母・於大の方と築山に居を構え始めて築山殿と呼ばれるようになるお瀬名が主導します。
酒井忠次が同席しているのは、後年の伏線でしょうか…。
そして選ばれたのが家康最初の側室である西郡局(お葉)でした。
西郡局は督姫を産みますが、母子共に有名な逸話や重要な出来事がありません。
選考過程やお葉が家と初夜を過ごす場面はコメディ要素が豊富でした。
驚いたのはこの回にLGBTQに関する要素を入れたことです。
唐突感が否めなく、描き方もザツな印象を受けました。
そもそもこの回の序盤に於大の方の口を借りて言わせたセリフが如何なものかと思うのですが…。
重ねて思うのですが、この回は必要だったのでしょうか?
おりしもこの回はWBCで日本対オーストラリア戦で大盛り上がりだった日でした。
WBCの大盛り上がりに反比例し、どうする家康の視聴率はガクンと落ち込み、とうとう一桁になりました。
私もWBCをリアルタイムで見ていましたので「どうする家康」は録画で見ました。
わざわざ時間をとって録画で見たら、無くてもいいんじゃね?と思うような回だったのはガッカリ感が否めません。
こうしたことがキッカケで脱落していきますので、この先は挽回できるのでしょうか?
どうする、NHK?
第11回 信玄との密約
第11回から本編に戻りました。ますます前回の第10回が何のための回だったのかが謎です。
さて、松平家が源氏に繋がる系図を必死に探しもとめ、祖先に得川の名が見つかったことから、家康は松平家康から徳川家康に改名します。
徳川家康に改名した家康は、織田信長に命じられて、信濃と三河の国境で武田信玄と直接面会します。
ですが、圧倒されて戻ってきます。まさにチビッてしまうのではないかという程の格の違いを見せつけられます。
信玄とは今川領の切り取りで合意をしますが、あっという間に駿府を落とした武田信玄に、家康主従は引間城(曳馬城とも)を武田家に取られないだろうかと慌てふためきます。
その引間城を守る城主はお田鶴の方。瀬名と幼馴染です。後半は、お田鶴の方の思いを描いたメロドラマが展開されました…。
メロウなドラマ仕立てでしたが、全く感情移入ができませんでした。
何故でしょう…。演出のせいでしょうか。映像のせいでしょうか。脚本のせいでしょうか。
さて、久々の感のある本多忠勝と榊原康政を見ると、そういえば服部半蔵はどうしたのだろうかと思わずにいられませんでした。
せっかく武田の忍びが出てきたのですから、服部党を登場させれば面白かったかもしれませんね。
2023年公開のドラマ・映画
大河ドラマ